 › kikito・・・湖東地域材循環システム協議会 › 2009年06月
› kikito・・・湖東地域材循環システム協議会 › 2009年06月2009年06月29日
kikito塾開催!!!
こんにちは。
kikito事務局です
今日はお知らせをしたいと思います。
第1回kikito建築塾へのお誘い
湖東地域材循環システム協議会/kikito建築塾
木造建築には様々な可能性があります。工法や材料についての選択肢も様々です。しかし、現実には、地域の暮らしと文化を育んできた伝統的な工法による木造建築が、建築基準法の改正を理由に隅に追いやられようとしています。
湖東地域には、古くから存続している地元職人の手による伝統的な建物がまだまだ残っています。地域づくりの点からも、炭素固定の観点からも、これらの建物を活かすことは、地域の暮らしを未来へつなげ、技術を未来へつなぐ大きな貢献ではないでしょうか?そのためには、懐かしさだけではなく、理論に裏付けられた取り組みも必要です。
今回、「湖東地域材循環システム協議会(kikito)」では、多賀町において「kikito建築塾」を開催することになりました。今年度多賀町の事業で活用される古民家を題材に、耐震性を高めるための評価方法と補強方法を学び、地域材の利用も併せて、実際の工事に応用していただけるような提案を行ないたいと考えております。
つきましては、下記の要領で勉強会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。
記
日時 2009年6月29日 19:00〜(1時間半〜2時間程度)
場所 多賀大社前駅前鳥居脇「北河邸」(この建物が題材となります)
<車でお越しの方は駅前の駐車場をご利用下さい>
地図:http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=%E5%A4%9A%E8%B3%80%E7%94%BA%E5%A4%9A%E8%B3%801322-1&sll=35.225779,136.28451&sspn=0.00922,0.013218&ie=UTF8&ll=35.225902,136.284285&spn=0.00922,0.013218&z=16&iwloc=A
<内容>建物の強度の評価と補強方法について(格子組実験ビデオ)、意見交換など
<講師>高田豊文先生(滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科高田研究室)
<主催>湖東地域材循環システム協議会/kikito建築塾
ご興味がある方は、ぜひお越しください。
詳しいことはkikito事務局までお問い合わせください。
kikito事務局電話番号 050-5801-0995
kikito事務局です

今日はお知らせをしたいと思います。
第1回kikito建築塾へのお誘い
湖東地域材循環システム協議会/kikito建築塾
木造建築には様々な可能性があります。工法や材料についての選択肢も様々です。しかし、現実には、地域の暮らしと文化を育んできた伝統的な工法による木造建築が、建築基準法の改正を理由に隅に追いやられようとしています。
湖東地域には、古くから存続している地元職人の手による伝統的な建物がまだまだ残っています。地域づくりの点からも、炭素固定の観点からも、これらの建物を活かすことは、地域の暮らしを未来へつなげ、技術を未来へつなぐ大きな貢献ではないでしょうか?そのためには、懐かしさだけではなく、理論に裏付けられた取り組みも必要です。
今回、「湖東地域材循環システム協議会(kikito)」では、多賀町において「kikito建築塾」を開催することになりました。今年度多賀町の事業で活用される古民家を題材に、耐震性を高めるための評価方法と補強方法を学び、地域材の利用も併せて、実際の工事に応用していただけるような提案を行ないたいと考えております。
つきましては、下記の要領で勉強会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。
記
日時 2009年6月29日 19:00〜(1時間半〜2時間程度)
場所 多賀大社前駅前鳥居脇「北河邸」(この建物が題材となります)
<車でお越しの方は駅前の駐車場をご利用下さい>
地図:http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=%E5%A4%9A%E8%B3%80%E7%94%BA%E5%A4%9A%E8%B3%801322-1&sll=35.225779,136.28451&sspn=0.00922,0.013218&ie=UTF8&ll=35.225902,136.284285&spn=0.00922,0.013218&z=16&iwloc=A
<内容>建物の強度の評価と補強方法について(格子組実験ビデオ)、意見交換など
<講師>高田豊文先生(滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科高田研究室)
<主催>湖東地域材循環システム協議会/kikito建築塾
ご興味がある方は、ぜひお越しください。
詳しいことはkikito事務局までお問い合わせください。
kikito事務局電話番号 050-5801-0995
2009年06月29日
第二回全体会議
こんにちは。
kikito事務局です
先日6月18日に大滝林業技術研修センターにて、第二回全体会議を行いました。
事務局員になり、初めての全体会議では協議会メンバーの方に直接お会いでき、やっとお顔とお名前が一致するようになりました。
事務局員の自己紹介をはじめとして、全体会議の本題へ。
今回の全体会議では、各部会長から今後の進め方を説明していただきました。
 ・安定供給部会
・安定供給部会
昨年は木が動かず年度末に100本程動いた程度。根幹が全く進まなかったので、
今年は木を大元のところで動かしたい。
木の必要量(人件)の調査、木材の山元が納得出来る価格帯の調査、川中の製材ストックのコスト(市場価格との差)を考える
 ・販売戦略部会
・販売戦略部会
CO2認証事業をカーボンシンクに再委託。kikitoの商品にするものの商品登録のガイドラインの決定。パンフレット・HP等でのPR活動。同時にペーパーの事業化を山口さん中心に動かしていく。
 ・コーディネート部会
・コーディネート部会
安定供給部会と販売戦略部会を繋ぐ役割を担う。人材育成に力を入れる。今回より薪を中心にした木質エネルギーも考える。資金調達。kikito塾開催(大工塾、森づくり塾)。ほかの部会の協力なしでは進まない。
各部会ごとのい熱い意見が飛び交い、こちらも熱くなりました!
この熱い想いを形にしていきたいです
協議会の皆様、遅くまでお疲れ様でした
kikito事務局です

先日6月18日に大滝林業技術研修センターにて、第二回全体会議を行いました。
事務局員になり、初めての全体会議では協議会メンバーの方に直接お会いでき、やっとお顔とお名前が一致するようになりました。
事務局員の自己紹介をはじめとして、全体会議の本題へ。
今回の全体会議では、各部会長から今後の進め方を説明していただきました。
 ・安定供給部会
・安定供給部会昨年は木が動かず年度末に100本程動いた程度。根幹が全く進まなかったので、
今年は木を大元のところで動かしたい。
木の必要量(人件)の調査、木材の山元が納得出来る価格帯の調査、川中の製材ストックのコスト(市場価格との差)を考える
 ・販売戦略部会
・販売戦略部会CO2認証事業をカーボンシンクに再委託。kikitoの商品にするものの商品登録のガイドラインの決定。パンフレット・HP等でのPR活動。同時にペーパーの事業化を山口さん中心に動かしていく。
 ・コーディネート部会
・コーディネート部会安定供給部会と販売戦略部会を繋ぐ役割を担う。人材育成に力を入れる。今回より薪を中心にした木質エネルギーも考える。資金調達。kikito塾開催(大工塾、森づくり塾)。ほかの部会の協力なしでは進まない。
各部会ごとのい熱い意見が飛び交い、こちらも熱くなりました!
この熱い想いを形にしていきたいです

協議会の皆様、遅くまでお疲れ様でした

2009年06月17日
kikitoペーパー
こんにちは。
kikito事務局です。
先日はコクヨ滋賀工場さんへご挨拶に行ってきました。
なぜ、コクヨさんなのか。。。
今年はKikitoペーパーの本格販売をしていきたいのです。
木から紙???
どのようにしていくんだろう???
なんて私は考えていました。
今回Kikitoペーパーは
多賀の間伐材を使って紙にしました
紙を作る工程を簡単に説明しますと…
丸太や、素材をチップという木片にします。
チップというのは、「ポテトチップ」にもあるように、薄片という意味です。
なんか想像しやすいですよね。
そのチップをパルプにします。
パルプから紙を作っていきます。
平成20年度にKikitoペーパーの試作をしました。
こんなに素敵なノートとメモが出来上がりました

他にも、コピー用紙も作りました。

メモには、ミシン目がついているので好評でしたよ。
今年からは、この商品を売っていきたい!!
と、考え!考え!考えています
実際に商品としてまわしていくと考えると
紙になるまでのお金や、配達などをどうするか。
商品を購入してくれる企業は確保できているのか。
お金の問題は難しいです。。。
ここで素敵なチラシを
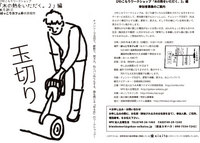 Kikitoのペーパーを使ってチラシを作ってくださいました。
Kikitoのペーパーを使ってチラシを作ってくださいました。
ありがとうございます
とっても優しくて、暖かいデザインですよね。
21日にイベントを開催されます
詳しいことは五環生活さんのHPをご覧ください。
http://gokan-seikatsu.jp/
これからKikitoペーパーが主流になればいいな
と思っております。
kikito事務局です。
先日はコクヨ滋賀工場さんへご挨拶に行ってきました。
なぜ、コクヨさんなのか。。。
今年はKikitoペーパーの本格販売をしていきたいのです。
木から紙???
どのようにしていくんだろう???
なんて私は考えていました。
今回Kikitoペーパーは
多賀の間伐材を使って紙にしました

紙を作る工程を簡単に説明しますと…
丸太や、素材をチップという木片にします。
チップというのは、「ポテトチップ」にもあるように、薄片という意味です。
なんか想像しやすいですよね。
そのチップをパルプにします。
パルプから紙を作っていきます。
平成20年度にKikitoペーパーの試作をしました。
こんなに素敵なノートとメモが出来上がりました


他にも、コピー用紙も作りました。

メモには、ミシン目がついているので好評でしたよ。
今年からは、この商品を売っていきたい!!
と、考え!考え!考えています

実際に商品としてまわしていくと考えると
紙になるまでのお金や、配達などをどうするか。
商品を購入してくれる企業は確保できているのか。
お金の問題は難しいです。。。
ここで素敵なチラシを

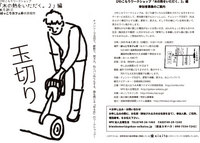 Kikitoのペーパーを使ってチラシを作ってくださいました。
Kikitoのペーパーを使ってチラシを作ってくださいました。ありがとうございます

とっても優しくて、暖かいデザインですよね。
21日にイベントを開催されます

詳しいことは五環生活さんのHPをご覧ください。
http://gokan-seikatsu.jp/
これからKikitoペーパーが主流になればいいな

と思っております。
2009年06月09日
たかとりふれあいまつり
 6月7日にたかとりふれあいまつりにKikitoのテントを出させていただきました!
6月7日にたかとりふれあいまつりにKikitoのテントを出させていただきました!朝からハイキングをする人と親子連れでにぎわっていました。

Kikitoの素敵なパネル

お客さんも、パネルを見て「何をしているところなの?」と質問してくださったり、木材を実際に使っている方と少しお話できたり。
いろんな職業、年代層の方々にKikitoの存在を知っていただけたんじゃないかなぁ。と思います。
まず、みなさんに知ってもらうことは大切だと感じました。
 木で作られた机の仕切り、モザイクのBOX、協議会の名札など作ってくださいました。木に印刷出来る技術はすごいです!写真で撮った花の色や、文字などにじまずハッキリ印刷されてます。
木で作られた机の仕切り、モザイクのBOX、協議会の名札など作ってくださいました。木に印刷出来る技術はすごいです!写真で撮った花の色や、文字などにじまずハッキリ印刷されてます。私も名札を楽しみにしています

 木の積み木、木のはがき(ちゃんと実際に届きますよ☆)、木で作ったバードコールも好評でした!
木の積み木、木のはがき(ちゃんと実際に届きますよ☆)、木で作ったバードコールも好評でした!バードコールは広い場所で聞くと、ほんとに鳥の泣き声に聞こえるんです
 子供も大人も興味津々でした!!
子供も大人も興味津々でした!!午前中で駐車場はいっぱいになり、大盛況でした!!
 ずっと見たかったささゆりを発見
ずっと見たかったささゆりを発見 咲いているのは、まだ一つか二つなかったのですが、つぼみはたくさんありました。
咲いているのは、まだ一つか二つなかったのですが、つぼみはたくさんありました。もう少し先が見ごろですかね。
見たことに満足してしまい、どんな香りがするのか匂ってくるのを忘れていました

また咲いたら匂ってみます。
ちなみに…
午後からKikitoの湯のみを陶芸で作っていました!
色は緑にしました。
大きさはエスプレッソカップになりそうです。もっと大きく作ればよかった。。。
まぁなんでも思い出ですよね!!
途中から皆様に存在を忘れられた横山が頑張って作りました(笑)
出来上がったら写真をアップしたいです☆
2009年06月08日
kikito事務局
はじめまして!
6月からkikito事務局員として働かせていただきます、小林と横山です。

まだまだ山や木について知らないことばかりなので、大滝山林組合の「やまのこ」を小学生と一緒に見学させていただきました。
 枝打ちの作業を実際に目の前で見せていただきました。
枝打ちの作業を実際に目の前で見せていただきました。
樹木の枝は製材した際に節として現れるのですが、この節の部分が生じないように、あらかじめ下層の枝を切り落としていく作業のこと。
ロープと木の棒で作られたはしごを器用に木にくくりつけて登っていく姿を見て「すごい!!すごい!!」と小学生と一緒にはしゃいでしまいました。。。
 次は木を実際に伐ってみることに!小学生たちも頑張ってお手伝い
次は木を実際に伐ってみることに!小学生たちも頑張ってお手伝い
今の時期に伐られたヒノキはみずみずしくて、表面の皮が簡単にペロンと剥けるんです!木というか果物みたいなか皮に剥けかたでした。
そして、いい香り~
Kikitoがこれからしていこう!とすることは…
山にお金を返そうという循環を作ることですが
伐ってどうする?
伐って、山から木を出すのに手間と人件費もかかり
出してきた木も何に使うのか。
さまざまの問題があって、問題の山にぶちあたっている気がしました。
が、逃げている場合でもないんです。
実際簡単にはいかないことで、自分たちがすごく大きなことに取り組むんだな!
と、改めて感じました。
そして、少しでも問題に山を越えていけたらいいな!
と感じた1日でした。
P.S
 チェーンソーアートも見せていただきました!あのチェーンソーで細かい細工をしていくんです!!
チェーンソーアートも見せていただきました!あのチェーンソーで細かい細工をしていくんです!!
熊の顔や、毛並みなんかも器用に表現されるんです
 迫力満点で見とれてしまいました。
迫力満点で見とれてしまいました。
6月からkikito事務局員として働かせていただきます、小林と横山です。

まだまだ山や木について知らないことばかりなので、大滝山林組合の「やまのこ」を小学生と一緒に見学させていただきました。
 枝打ちの作業を実際に目の前で見せていただきました。
枝打ちの作業を実際に目の前で見せていただきました。樹木の枝は製材した際に節として現れるのですが、この節の部分が生じないように、あらかじめ下層の枝を切り落としていく作業のこと。
ロープと木の棒で作られたはしごを器用に木にくくりつけて登っていく姿を見て「すごい!!すごい!!」と小学生と一緒にはしゃいでしまいました。。。
 次は木を実際に伐ってみることに!小学生たちも頑張ってお手伝い
次は木を実際に伐ってみることに!小学生たちも頑張ってお手伝い
今の時期に伐られたヒノキはみずみずしくて、表面の皮が簡単にペロンと剥けるんです!木というか果物みたいなか皮に剥けかたでした。
そして、いい香り~

Kikitoがこれからしていこう!とすることは…
山にお金を返そうという循環を作ることですが
伐ってどうする?
伐って、山から木を出すのに手間と人件費もかかり
出してきた木も何に使うのか。
さまざまの問題があって、問題の山にぶちあたっている気がしました。
が、逃げている場合でもないんです。
実際簡単にはいかないことで、自分たちがすごく大きなことに取り組むんだな!
と、改めて感じました。
そして、少しでも問題に山を越えていけたらいいな!
と感じた1日でした。
P.S
 チェーンソーアートも見せていただきました!あのチェーンソーで細かい細工をしていくんです!!
チェーンソーアートも見せていただきました!あのチェーンソーで細かい細工をしていくんです!!熊の顔や、毛並みなんかも器用に表現されるんです

 迫力満点で見とれてしまいました。
迫力満点で見とれてしまいました。


